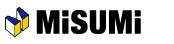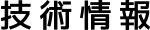射出成形用部品
- 射出成形の条件として、樹脂温度と保圧がありますが、これらには密接な関係があります。射出成形が可能な領域、言い換えれば良品が成形加工できる領域は、無限にあるわけではなく、ある一定範囲の前提が満たされた場合に限定されます。 【図】には、樹脂温度と保圧の2元関係を図示しています。 この図からは、次のようなことが判ります。
- 樹脂の射出成形加工では溶融させた樹脂の流動性の善し悪しによって成形条件、特に射出圧力や射出速度、金型温度の設定が大きく左右されることは皆さんも良く体験していることかと思います。 樹脂の流動性を評価する方法にはいくつかの方法がありますが、最も簡易的で目安として利用されているものがメルトフローレート(Melt Flow Rate, MFR)です。 メルトフローレートは、樹脂の試験材料(ペレット)をメルトフローインデクサーという試験装置へ装てんし、加熱して規定の重量で溶けた樹脂を流出させてその流れ出た樹脂量を計測して指標とします。試験方法はJIS,ISOで規定されています。 メルトフローレートの数値が大きい樹脂ほど流動性が良いと評価されます。メルトフローレートが小さい樹脂は流れが悪いです。 ただし、メルトフローレートは、静的な状態での流動性を評価するため、実際の射出成形の場合は極めて短時間で狭いゲートを流動しますのでメルトフローレートの値はそのまま射出成形の場合にぴったりと適合する訳ではありませんのでこの点は理解をしておく必要があります。タグ:
- 一般に、成形サイクルを構成している要素は、下記が挙げられます 1.型閉時間 金型が閉まるまでの時間です。金型の開閉時間は、射出成形機の型開きストロークと型閉速度によって左右されます。 金型は、質量がありますので、無闇に型閉速度を早くしすぎますと、金型が閉じる時に運動エネルギーにより金型が破損する可能性がありますから、ブレーキをかけることを考える必要があります。 2.充填時間 充填時間は、スプルーから流入した溶融樹脂がキャビティの中を完全に充填するまでの時間です。 充填時間は、射出成形機の射出速度(実際には、射出スクリューまたはピストンの移動速度と射出シリンダー直径によって決まる、射出体積/時間=射出率(cm3/sec))によって左右されます。 また、溶融樹脂の粘度によっても左右されます。充填時間が短いと樹脂の充填速度が速くなりすぎて、樹脂焼けやガスを発生させることがあります。一方、充填時間が長すぎると成形品の表面にフローマークやウエルドが明瞭に現れてしまうことがあります。タグ:
- エンジニアリング・プラスチック(エンプラ)やスーパー・エンプラの中には、キャビティの表面温度が100℃を超える種類の樹脂が増えてきています。 キャビティの表面温度が90℃ぐらいを超えてしまいますと、水(お湯)による温度調節では通常、昇温と温度保持が困難になります。 一般には、下記の手段が採用されます。 (1)油温度調節 油による温度調節は、型板やキャビティに設けられた流路に、循環ポンプから吐出された油が、ジョイントホース経由にて循環することにより、温度を一定に保ちます。一旦、設定温度まで温度が上がってしまいますと、比較的安定した温度維持が可能です。 しかし、温度の立ち上がりには時間を必要とする短所があります。 また、油の取扱いは、やけどの危険性があり、さらに油の後処理が面倒であるといった点も懸念されます。 (2)電気ヒータ温度調節 電気ヒータ(カートリッジヒータ)による温度調節は、温度センサ(熱電対等)と併用することにより、温度を一定に保ちます。熱容量が大きいので温度の立ち上がりが早い利点があります。タグ:
- 射出成形に使用される熱可塑性樹脂(Thermoplastic resin)は、金型の中に加温されて液状になった状態でキャビティ内へ注入されて、金型の表面に接触することで熱量を奪われて冷却され、固化します。 このときに、液体のときの体積は、固化する際に体積収縮を起こして縮みます。この現象を「成形収縮」と呼んでいます。英語ではshrinkageと言います。 成形収縮は、プラスチック射出成形品を作る上では大変重要な物理現象です。所望の寸法や形状の射出成形品を生産するためにはこの物理現象を的確に理解しなければなりません。 さらに、射出成形金型の設計や機械工作をする際には、成形収縮を考慮した寸法と寸法公差でキャビティなどを作る必要があります。 成形収縮は、熱可塑性樹脂の種類によって大きく範囲が決定されます。つまり、樹脂の種類によって収縮率は左右されます。しかし、樹脂の種類以外にも以下の要素を考慮しなければなりません。
- プラスチック樹脂が商品として世の中で活躍するためには、商品用途に合わせた特性を備える必要があります。樹脂に求められる特性としては以下のような内容があります。金属材料とはまた異なる特性を有しなければならない場合もあります。タグ:
- 人体の手術用具や人工臓器の材料として高分子材料が使用されることがあります。高分子材料は軟質で、変形しやすく、また透明であったり、生分解できるなどの特殊な性質を持つ素材もあり、病気の治療や手術でこれらの素材が活躍する場面も増えてきています。 生身の人体に直接接触して使用される治療用材料を生体高分子(biomedical materials)と呼んでいます。 生体高分子は、人体に対する安全性が確保されていなければなりません。人体は、拒絶反応(forein body rejection)を起こしたり、素材から溶け出すイオンや低分子化合物による毒性反応が発生する可能性がありますので、素材の実用化には長い間の安全確認評価が必要になります。 主要な生体用高分子材料を以下に示します。タグ:
- プラスチック成形材料の中で、熱可塑性樹脂を射出成形によって金型のキャビティ内へ流動させる場合、溶けた樹脂はある粘度を持った流体としてスプルー、ランナー、ゲートそしてキャビティ内を流動します。流動抵抗によって樹脂の流速や圧力は変化します。そして、樹脂の粘度は金型の表面に接触することによって温度がだんだん低下していって、粘度も時々刻々と低下していき、最後には流動ができない状態まで粘度が低下していきます。 流動ができなくなるまで冷却されてしまいますと射出成形加工がそれ以上不可能になってしまいます。このように熱可塑性樹脂の射出成形加工では樹脂を流動させることができる距離が成形品の厚さやランナーサイズに左右されることがわかります。
- 射出成形加工されたプラスチック成形品は、2以上の成形品どうしを後加工で接合して製品にすることがしばしば行われます。一回の射出成形で加工できればよいのですが、アンダーカット形状がある場合などは2部品を作ってから、溶接などで接合しなければならない場合もあります。 プラスチック成形品の接合加工法としては以下の方法があります。 1.熱接着法 金属板を電熱ヒーターで加熱して、成形品を加圧して融着させる方法です。フィルムや袋などで多用されています。 2.瞬間熱接着法 熱接着法の一種ですが、金属リボンヒータに加熱して融着させます。金属リボンヒータは細いので加熱と冷却に要する時が瞬間になりますので、接合部がきれいにしっかりと接合させることができます。 3.ホットジェット 電熱ヒーターを内蔵したエアーブロー装置から熱風を送り出してプラスチックを融着させる方法です。ヘアドライヤーと類似した方法です。溶接棒を用いて肉盛りしながら接合させることもできます。 4.高周波誘電加熱接着法 高周波を送ることでプラスチックの部分を加熱して接合させる方法です。フィルム、シートの接合で多用されています。タグ:
- プラスチック材料の金属に対する一般的な弱点は、耐熱性が十分でない点があります。しかし、最近の実用化研究によって、耐熱性は飛躍的に改善され、荷重たわみ温度が400℃に達する樹脂も量産が始められています。 耐熱性高分子は、温度によって軟化したり、融解しないようにするためには、無定形高分子ではガラス転移点(glass transmition temperature, Tg)が高い必要があります。また、結晶性高分子では融点(melting point, Tm)が高い必要があります。 融点は、固体と液体が平衡状態にある温度なので、自由エネルギーが0になる温度であるとも言えます。 そこで、融点Tmは、下記の式で表すことができます。 Tm=△Hm/△Sm △Hm:融解時のエンタルピー △Sm:融解前後のエントロピーの変化 △ Hmは、融解に要する熱エネルギーであるので分子間力に関係します。これを大きくするには水素結合によって強い分子間力が働くアミド基の導入が検討されます。分散力も強い分子間力なので、揺らぎやすい電子を持った共益二重結合、ベンゼン環の導入も効果が見られます。タグ:
- 熱硬化性樹脂は、射出成形に使用されている熱可塑性樹脂とは異なり、加熱されると一瞬液化しますがその後硬化する特性を持った樹脂です。 熱硬化性樹脂には下記のような種類があります。 -フェノール樹脂 -ユリア樹脂 -メラミン樹脂 -不飽和ポリエステル樹脂 -エポキシ樹脂 熱硬化性樹脂の成形では、圧縮成形やトランスファー成形が一般的で、射出成形はごく一部に限られています。熱硬化性樹脂の成形では、成形材料を金型内に投入した後で金型温度を150℃程度に加温します、そうすると材料は一瞬溶けて液状になりますが、その後は加熱による化学反応で固化します。一度固化してしまうとその後は液状に戻ることはありません。つまり、冷却は不要で成形品を金型から取り出すことができます。 しかし、材料の投入量がばらつくことから成形品の周囲には余分に漏れ出した材料がばりになって付着しますので、ばりの処理が必要になります。 また、硬化する途中で材料からガスが発生しますので、これを金型を少し空けてガス排気をする工程が必要になる場合があります。タグ:
- プラスチック射出成形機でプラスチック材料を溶かして射出できる状態することを可塑化と呼んでいます。今日の射出成形機ではスクリューインライン方式(Screw In-Line)が可塑化装置の大半を占めています。 スクリューは、耐摩耗性、耐食性、高強度の金属材料で作られており、その表面には特殊なコーティングを施しているものもあります。 スクリューは、材料ペレット(粒)を加熱シリンダー内に食い込ませて前進させるためにらせん溝が機械加工されています。 らせん溝は、以下の部分で構成されています。 1.供給部 供給部は、ペレットがホッパーから重力で落下してきたものを加熱シリンダー内に導いて、その間にペレットを余熱して圧縮部で溶かすための準備をする部分です。 2.圧縮部 圧縮部は、らせん溝が徐々に浅くなるように機械加工されています。そして余熱されたペレットがさらに加熱されて溶融します。溶融しながらペレットに巻き込まれていた空気や発生したガスは、らせん後部からホッパー側へ排気されます。 3.計量部 計量部は、溶けた材料をさらに混合して均一に溶けるようにする部分です。タグ:
- プラスチック射出成形金型を成形加工で連続使用しているとエジェクタピン、エジェクタスリーブとセンターピンスライドコアなど移動する部品の一部が作動不良を起こす場合がります。 作動不良は、摺動面の異常磨耗によって引き起こされる場合が大半です。異常磨耗はその原因により下記のような分類をすることができます。 (1)アブレシブ磨耗 移動する部品の材質に硬度の差がある場合に生じやすい異常磨耗です。 硬い材料が柔らかい材料に食い込んでひっかき(スクラッチ)を起こし、焼き付く現象です。 (2)凝着磨耗 金型部品の凸部分がぶつかり合って最も接触が激しい箇所が凝着を起こし、凝着部分が脱落して磨耗粉になり、磨耗が進行する形態です。金型部品の表面は一見滑らかに見えますが、実際には微少な凹凸があります、これらの凹凸の中で凸起部分が先に接触し、微小部分に摩擦熱が集中して作用し凝着を起こすメカニズムだと考えられます。
- ポリ乳酸樹脂(Poly Lactic Acid, PLA)は、原材料を植物のでんぷんや糖を100%用いる植物由来樹脂で、石油系原材料を一切使用しない環境に優しい合成樹脂です。しかも、廃棄後は土の中に天然に存在しているバクテリア(微生物)の酵素によって、水(H20)と二酸化炭素(CO2)だけに完全生分解される素晴らしい特性を持っています。水と二酸化炭素は、植物の葉緑体によって光合成を経てでんぷんや糖に戻ります。つまり、ポリ乳酸樹脂は、半永久的に炭素の形を変えただけで循環していることになり、カーボンニュートラルな理想の環境素材として活用が可能です。タグ:
- PET樹脂とは、ポリエチレンテレフタレート樹脂の略称です。 PET樹脂は、溶融温度が270℃近辺で、成形温度は、270~280℃であり、比較的高温で射出成形を行います。この樹脂の特徴の一つとして、流動性があります。融点以上では流動性が良好ですが、固化が始まると一気に流動がしにくくなります。つまり、樹脂温度の変化と流動性が密接に関係しているということになります。金型の温度管理、樹脂温度管理は、PET樹脂には必須の項目になります。多くの場合、PET樹脂の射出成形ではホットランナーが使用され、さらにバルブゲートが選択されます、これは、ゲートの開閉遮断を機械的に行うことで流動の管理を確実にしたいがためなのです。 流動が良好なので、金型のクリアランス管理や充填圧力による金型の変形にも配慮が必要になります。特にホットランナーのマニホールドデザインでは、変形防止、熱膨張代の管理などがポイントになります。 また、PET樹脂は、水分に敏感に反応しますので、成形材料のペレット予備乾燥は徹底して行い、管理レベルも高くしなければなりません。水と反応すると加水分解を起こします。したがって, PET樹脂の射出成形では材料予備乾燥装置が必須になります。タグ:
- プラスチック成形材料は、高分子からできあがっていますが、その化学式によっておおまかに以下のような傾向があることが知られています。