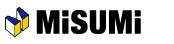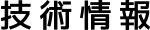射出成形用部品
- プラスチック成形品は、成形加工後に二次加工として塗装や色入れなどの色彩を付与することで付加価値を高める工程を採用する場合があります。文字やロゴマークの印刷、ウエルドラインやフローマークを目立たなくするための表面塗装、金属光沢を得るためのメタリック塗装などがあります。 塗装は塗料やインキを使用するのが一般的です。これらの組成は、ビヒクル、助剤及び顔料から構成されています。 ビヒクルは、樹脂と溶剤と添加剤を混合させたものです。 平板インキでは、樹脂としては石油樹脂、ロジン変性フェノール樹脂が主に使用されます。 グラビアインキでは、アクリル樹脂、ポリアミド樹脂が主要な樹脂になります。 塗料では、アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂が使用されています。 溶剤としては、平板インキでは高沸点石油系炭化水素溶剤が使用されています。 グラビアインキでは、イソプロピルアルコール、酢酸エチル等が採用されています。塗料ではキシレン、酢酸エチル、イソプロピルアルコールが利用されます。 助剤には、粘度調整剤、ゲル化剤、乾燥調整剤、可塑剤、滑剤、静電気防止剤、界面活性剤、消泡剤などがあります。タグ:
- プラスチック射出成形金型では、溶けたプラスチック材料を流動状態のまま金型の内部へ流入させてキャビティ内を充填し、充填完了後は冷却固化させて、成形品の形状に固定させるプロセスを経ることになります。 この一連のプロセスの中で、流動状態の間はキャビティの温度は高いほうが流動性が良く、低い圧力で安定した充填が可能になります。一方、冷却固化させる場合には、成形サイクルを短縮させて経済効率を改善させるために、なるべく低いキャビティ温度であることが望ましいです。 このようなキャビティ表面温度のコントロールを、数秒から数十秒の時間内で対応させることは、通常の金型構造では簡単なことではありません。 一般的には、上記のような相反するキャビティ表面温度のコントロールを折衷した温度帯を選定して、水冷やカートリッジヒーターで温度コントロールをしています。 また、キャビティ表面の温度分布に関しては、なるだけ温度差の小さな分布であることが収縮状態を安定させ、そりや変形、表面光沢などの差を少なくするのに有用です。結晶性樹脂の場合には、結晶粒の大きさや分布の安定化にも有効です。 プラスチック射出成形用金型の温度コントロールに関しては熱の移動について、次の3つの形態が考えられます。
- プラスチック射出成形品の表面の硬さを試験するため方法として一般的に使用されているのは、ロックウエル硬さ試験です。 金型部品用の鋼材の試験方法としてロックウエル硬さ試験は多用されていますが、この場合の測定スケールはCスケールで、硬さは「50HRC」のように表記されます。 プラスチック成形品の硬さを測定する場合、Cスケールを使用した場合には鋼材と比較して大変柔らかいために正確な硬度を計測することができません。 そこで、プラスチック成形品の硬度を測定するためには「Rスケール」または「Lスケール」、「Mスケール」を使用します。 したがって計測した値は、「65HRR」、「80HRL」、「92HRM」のように表記されます。 各スケールは、以下の計測基準によって使い分けられます。タグ:
- バクテリアや生物によって生分解されるプラスチックが開発されて、さまざまな素材が使用されるようになってきています。生分解性プラスチックで、現在利用が始められているものには、以下のような材料があります。タグ:
- プラスチック材料は、過度の熱エネルギーを受け、高温になると燃焼をする材料が多い特徴があります。したがいまして、プラスチック材料の燃えやすさ(燃えにくさ)は様々な試験方法によって定義され、その素材が燃焼環境的に使用可能かどうか判断する指標となっています。 プラスチックの燃焼に関する試験方法や法令には世界各国で様々なものが規定されています。実際にプラスチック材料を選定する場合にはこれらの規格についてどのレベルを満足しなければならないかを顧客や社会的責任と照らし合わせて検討をする必要があります。 現在、世界各地で採用されている主な法令や試験方法には、下記のようなものがあります。
- プラスチックは、ある特定の溶剤に対して溶解したり、残留応力(ストレス)が残っている場合に亀裂(クラック)を生ずる場合があります。これはプラスチック自身が石油化学的に生成される物質であることから、特定の溶剤と化学的に反応してしまうために生ずる現象です。 下記のプラスチックでは、以下のような溶剤に対して、クラックが発生する危険性があります。
- 医療器材用プラスチックには、高い安全性や信頼性の他にも使用用途を満足させるために、様々な角度からの物性が必要になります。例えば、下記のような物性が医療器材の備えるべき特性として必要になってくるのです。タグ:
- 注射器や薬瓶などの医療用器材には、プラスチックが多用されうようになってきています。医療用器材は、私たちの健康を守り、病魔から逃れるための医療を実施するために必要不可欠な道具であり、そのような人体に直接関与する部品でもあるために、安全性、信頼性が科学的に保証されている必要があります。 また、最近の新たな感染症の出現等とも関連して、一度使用された医療用具を洗浄、消毒して再使用することは限定され、使い捨て(ディスポーザブルタイプ)のプラスチック製医療器材が多用されるようになってきています。使用済みプラスチック製医療器材は、廃棄後の燃焼処理で有害物質が発生しない工夫も素材自身には要求されており、使用時と廃棄後の社会的に要求される特性を満足しなければならず、プラスチック素材もそのような意味から限定されることになります。 日本におけるプラスチック製医療器材に使用されている主なプラスチックには、以下のような種類があります。タグ:
- シクロオレフィンポリマーは、透明度が優秀で、耐熱性があり、金型の表面転写性も良好なため、レンズ類の射出成形品として採用事例が増えてきています。 フラットパネルディスプレイ(FDP)用導光板、光ピックアップレンズ、ディスクなどの光学部品に多用されています。薄型液晶テレビや携帯電話端末関連の光学部品への応用が急増しています。 その背景には、下記のような優れた特性があるからです。 1.優秀な透明性 アクリル樹脂やポリカーボネート樹脂と比較して全光線透過率が優れていて、透明性が優れています。したがってレンズや導光板の機能としては、最適な特性を持っていると言えます。 2.金型内の樹脂流動性が良好 透明樹脂であるPMMAやPCは、射出成形時の金型内での樹脂流動性が悪く、成形加工が困難でしたが、シクロオレフィンポリマーはPCの4倍程度、PMMAの約1.5もメルトフローレートが良好ですので、低い充填圧力で射出成形が可能です。成形品に残留応力を残しにくく成形品の光学特性にも良い方向に作用します。 金型表面の微細形状の転写性にも良い影響を与えますので、マイクロストラクチャ形状の転写には適しています。タグ:
- プラスチック射出成形品の表面には静電気を帯びる性質があり、静電気に引き寄せられて、空気中のほこりや異物が付着することがしばしば問題となります。 プラスチック射出成形における静電気は、金型のキャビティから離型する際に成形品表面とキャビティ表面が接触したり、摩擦によって帯電するパターンが多いようです。 静電気には帯電列というデータが知られており、帯電列は2つの物質を摺り合わせた際にプラス側の電位を帯びるのか、マイナス側の電位を帯びるのかを知るための指標となっています。 (例:ポリアミドと木綿を摺り合わせた場合、ポリアミドが+に帯電し、木綿は−に帯電します)
- ポリカーボネート樹脂は、透明な高強度エンジニアリングプラスチックとして、さまざまな成形品に使用されています。耐衝撃性、寸法安定性も良好ですが、一部の溶剤については分解してしまう弱点があります。このような長所と短所を考慮して、広範囲な分野で実用されています。 近年ではポリカーボネート樹脂の需要量は増加の一途をたどり、今後も需要は増えていくと予想されます。 金型設計上では、流動性が極端に悪い点、金型温度を高めに設定しなければならない点、離型対策を十分に検討しなければならない点、鏡面仕上げが必要な場合には鋼材の選定等の技術課題があります。 最近では大型成形品にポリカーボネートを採用する例が増えており、このような場合にはバルブゲートを採用して金型内樹脂温度の低下を防止し、流動性を改善させる技術が開発されています。 最近の実用化されている成形品には次のようなものがあります。タグ:
- 液晶ポリマー(LCP、Liqud Crystal Polymer)は、良好な耐熱性を有するスーパーエンジニアリングプラスチックとして電子部品、コネクターに採用されています。 液晶ポリマーは、成形品が薄肉であっても良好な流動性を示しているため、コネクター類などの薄肉小型精密成形品の射出成形も可能です。 表面実装方式(SMT)ではんだ付けされる部品では、今後、「鉛フリーはんだ」が環境対策として推奨される社会情勢があり、「鉛フリーはんだ」はSMT時の温度が260℃程度まで上昇させなければならないため、従来他の樹脂で使用されていた電子部品が液晶ポリマーに変更される例が増えてくると予想されています。 現在の日本での液晶ポリマーの需要量は年間9,000トン程度と推測されています(2006年)が、今後3年ぐらいの間には需要量は30%程度増加するという予測もあります。 液晶ポリマーは優良な耐熱性、薄肉流動性を有する反面、以下のような成形加工上の難点があります。 (1)ウエルド強度 液晶ポリマーは流動性は良好であってもウエルド部の密着強度が低いという欠点があります。金型設計上ではこのポイントをいかに克服する構造を採用するかが重要な部分になります。タグ:
- 最近の射出成形用プラスチックは、高耐熱性、高強度を兼ね備えた素材が増えてきている結果、融点が高くなる傾向が顕著であり、したがって射出シリンダーの設定温度も高くしなければならない場面が増えてきています。 そのような傾向に沿って、金型の保持温度も高温に設定しなければならない場面が増えてきています。 樹脂の溶融温度が300℃を越えるような場合には、金型温度は120〜200℃付近の温度域に設定しなければならないケースが多いです。そうしますと、型板やキャビティの熱膨張が大きくなり、金型の開閉に際しては、スムーズな動作ができなくなる場合があります。 熱膨張による寸法の変化量は、金型の大きさに比例しますので、大きなサイズの金型では0.2ミリ級の寸法変化が生じる場合もあります。また、厄介なことに可動側と固定側では型板の厚みや形状が異なっていますから、熱容量も必然的に差が生じ、金型の熱膨張による狂いは不均等になってしまいます。 このような状態で金型を開閉すると、ガイドピンとガイドブシュの間でかじりをしょうじたり、異音が発生し、最悪の場合には金型を開閉することができなくなる場合があります。 このような状況をクリアーするためには、以下の方策を採用することが実務上では有効です。タグ:
- 熱可塑性エラストマー(TPE、Thermo Plastic Elastmer)は、射出成形が可能なゴム状の成形材料で、各種の用途で実用化されています。 熱可塑性エラストマーには、いくつかの種類があって、特性ごとに応用分野が異なってきます。 以下に主な種類と特性を紹介します。
- 射出成形加工が可能な生分解性プラスチックの代表格として、ポリ乳酸(Poly Lactic Acid,PLA)があります。 ポリ乳酸は、さつま芋やじゃが芋、とうもろこしなどのでんぷんを素材とし、乳酸菌による発酵プロセスを経て、化学合成される植物由来のプラスチックです。射出成形が可能で使用後は、土中へ埋設することで、バクテリアによる生分解によって、水と炭酸ガスのみに分解されます。 つまり、「空気中の二酸化炭素と水」が植物によって光合成され、炭水化物(でんぷん等)に変化し、乳酸菌の活躍によってポリ乳酸に変化し、バクテリアの酵素によって、水と二酸化炭素に再度生分解されます。 このようにポリ乳酸は、地球環境の保護に大いに期待されているプラスチックです。 最近では、ポリ乳酸のアプリケーション素材の研究開発が進んでいて、以下のような素材が開発されるようになってきています。タグ:
- プラスチック原材料の中でも最近、射出成形材料として使用される頻度が多くなっている材料としては、次のようなものがあります。当然に、これらの材料を使用する金型の新規生産も、増加していると考えて良いと思います。 (1)ポリカーボネイト(PC) 国内生産量41万トンと大量に生産されており、液晶テレビモニター、DVDプレーヤー、携帯電話筐体、導光板、TFT関連、電池パック、プリンター部品、自動車用照明部品などに採用されている。 透明度が良好で、高強度、高耐熱性であるが、成形加工性は悪く、流動性が低いので、高い圧力で金型内に充填させなければならない。金型温度も高く設定する機構が必要になる。 最近では、バルブゲートを使用することで、これらの問題を解決する技術も登場している。 (2)ポリフェニレンサルファイド(PPS) 国内生産量2万トンもの生産量になり、表面実装対応耐熱電子部品、光ピックアップ、自動車部品等へ使用されている。ガラス繊維を混ぜて使用する例も多い。流動性は良好である反面、僅かの金型の隙間でも流入しやすいのでバリが発生しやすい。金型温度は150℃程度にまで上げなければならない。 需要に対して生産が追いつかない状況が続いている。タグ:
- プラスチック射出成形機の型締め力が5〜20トンクラスの小型成形機が、国内外で好調に導入されるようになってきています。 これらの小型成形機を使用して、微細で精密な樹脂成形品を生産する需要が急速に伸びているためです。 また、さらに1ランク小さな成形品の成形加工は、「マイクロ成形」と呼ばれています。 マイクロ成形は、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems、マイクロ電子機械システム)やマイクロ化学等の分野で使用される微細プラスチック部品を生産するために使用されます。 このような小型成形機やマイクロ成形機で使用される金型は、従来使用されている金型よりも一回り小さく、精密に工作されている必要があります。 具体的には、下記のような部分についての要素技術が重要になってきます。タグ:
- 成形品を金型から取り出すためには、一般的にエジェクタピンやストリッパープレートを使用します。 成形品を取り出すためには、成形品が金型に密着して残存しようとする力(離型抵抗)よりも大きな力で成形品を移動させる必要があります。 成形品が金型から外れるための離型抵抗は、以下の要素が関連してきます。 成形収縮 キャビティ表面の表面粗さ 抜き勾配 成形品の潤滑性 成形品とキャビティ表面の間の真空度 成形品の表面温度 また、取り出しの手段としては、次のような方法が使用されています。タグ: