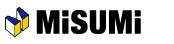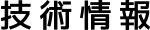メカニカル部品
- 機械類の設計段階で安全性を盛り込むための技術原則がJIS B 9700-2(設計の基本概念)に規定されています。安全性設計のチェック項目として利用できます。(JIS B 9700-2は廃止され、JIS B 9700 (2013)に統合されました。) (1)機械設計に関する一般的技術知識(参考文献:JISハンドブック(72)機械安全) 下記の検討項目は一般事項として必要とされています。 a)機械的応力 ・適正な計算、構造および締め付け方向による応力制限。 Ex.ボルト締め組立、溶接組立 ・過負荷防止(Ex.“可溶”プラグ、圧力制限バルブなどで)による応力制限。 ・応力変動(特に、繰返し応力)下にある要素の疲労の回避。 ・回転要素の静的および動的バランス b)材料およびその特性 ・腐食、経年変化、摩滅および磨耗に対する抵抗性 ・かたさ、延性、ぜい(脆)性 ・均質性 ・毒性 ・引火性 c)次についてのエミッション値 ・騒音 ・振動タグ:
- 自動機や工作機械などの設計者は、機械の設計段階で設計中の機械の危険度合いを自己評価できる能力が必要です。この自己評価能力を育成・向上させるプロセスツールとして、JISの「安全性達成のための反復的プロセス」が有効に活用できます。(JIS B 9702は廃止され、JIS B 9700 (2013)に統合されました。下図は「ステップメソッドによる反復的リスク低減プロセス説明図」の中に統合されています。) (1)リスクアセスメント ・リスクアセスメントとは、機械類に付随する危険源の審査を統計的方法で実施可能にするための一連の論理的手法です。 ・リスクアセスメントは、次の2つの調査で成り立っています。 1)リスク分析 2)リスク評価 ・リスクアセスメントの調査結果を受けて、リスク低減の対策行動が取られます。このためリスクアセスメントには「リスク低減の行動」は含まれません。 (2)安全性達成のための反復的プロセス 次の行動プロセスでリスクの分析・評価とリスク低減活動が繰り返され、その結果として、機械類の設計製作過程での安全ノウハウが蓄積できます。タグ:
- 機械の本質安全化の考えを前号で解説しました。ここでは、プレス装置やかしめ装置などの構造の装置を事例に本質安全化を解説します。 (1)機械の本質安全化とは 機械の本質安全化とは次の3項目を含む対処策です。 1)安全設計が機械設備に内蔵され、または組み込まれている。 2)機械装置の操作や取扱いを誤っても、事故や災害に繋がらないように、フールプルーフ機能を有している。 3)機械設備や部品が破損や故障しても安全側に作動するようフェールセーフ機能を有している。 (2)プレス装置/かしめ装置の場合の本質安全化 ・プレス装置やかしめ装置などの場合、事故のほとんどは、1)材料の供給作業、2)材料の位置調整・修正などの作業のために加工点に手を入れたときといえます。 ・この様な場合の負傷は、多くの場合が後遺症として残る災害のため本質安全化が必要です。 ・本質安全化ができない場合には、次の方策として安全装置の取付けとなります。タグ:
- 自動機や工作機械などの機械系の安全については、JISハンドブック(72)で「機械安全」として規定があります。以降では、機械類の安全設計について解説します。 (1)機械の本質安全化 機械の本質安全化とは次の3項目を含む対処策といえる。 1)安全設計が機械設備に内蔵され、または組み込まれている。 2)機械装置の操作や取扱いを誤っても、事故や災害に繋がらないように、フールプルーフ機能を有している。 3)機械設備や部品が破損や故障しても安全側に作動するようフェールセーフ機能を有している。 (2)機械設計者の本質的安全設計方策 ・事故などのリスクを減らす方策としては、a)機械設計者が行う安全設計方策、b)使用者が行う方策の2つがあります。 ・a)の機械設計者の安全設計方策は次のような内容です。 1)本質的安全設計方策<下記> 2)安全防護および付加保護方策 3)使用上の情報 ・b)の使用者の方策は、下記などがあります。 4)安全向上組織 5)保護具の使用 6)訓練タグ:
- 卵の形状は、未来の自動車の形状コンセプトとして何度か利用されています。エスティマ(トヨタ)の初代スタイルは、「天才タマゴ」と呼んだ卵型の丸みを帯びたボディー形状でした。この卵の形状とその構造について解説します。(参考文献:尾田十八著:形と強さのひみつ、オーム社) (1)卵の形状/構造/特徴とその仕組み 1)卵の形状/構造 ・ニワトリの卵の形状は、長径=58~62mm、短径=45~47mmの楕円体です(【図1】参照)。 ・殻の厚さは、0.36mm程度の卵殻と0.08mm程度の卵殻膜の合計厚さ=0.44mm程度で、短径の約1/100の厚さしかありません(【図1】参照)。タグ:
- これまで、材料の軽量化と構造の軽量高強度化の2つの手段での軽量化技術を解説しました。ここでは、両者を同時に検討しながら最適な形状設計で軽量高強度を実現させるアプローチを解説します。 (1)自動機の軽量高強度構造の設計の進め方 自動機などの装置構造は次の2つの要素に区分できます。 (2)最適な形状設計で軽量高強度を実現させるアプローチ ・上記の2つの構成要素をさらに細かな課題に展開し全体の設計課題を把握します。 ・この全体の課題を念頭に置きながら、過去の類似構造の長所と短所をチェックし、軽量高強度構造化を進めることが失敗の少ないアプローチです。タグ:
- 前回で「軽くて強い構造部材」の例で竹を紹介しました。この竹の中空構造が曲げの力に対して強いことを示す技術用語に「断面二次モーメント」があります。ここでは、この断面二次モーメントについて分かりやすく解説します。 (1)構造部材の強さの表現 強さの表現には次のような数種類の用語があります。 竹の場合は、節を持つ中空円筒構造のために大きな「剛さ」を持ち、また、円筒表面に近くなるほど緻密な組織構造となっていることから高い「靭性」も持っており、両者を合わせ持っていることから軽くて強い構造部材といえます。タグ:
- 構造部材の軽量化技術で肉抜きや中空構造化は良く使われる手段です。ここでは、中空構造化の効果を「竹の構造と強さ」の関係から解説します。<参考文献:尾田十八著、形と強さのひみつオーム社出版局>タグ:
- 金属材料をプラスチックに置き換える手段が材料置換の軽量化技術の典型例です。これまではエンジニアリングプラスチックで金属部分を置き換えることが実施されています。 (1)エンジニアリングプラスチック(Engineering plastics)とは ・耐熱、耐じん性、耐薬品性、耐難燃、耐候性などが高く、寸法安定性と機械的物性を高温でも保持する材料のため構造材に使用できる優れたプラスチック材料をエンジニアリングプラスチックと呼びます。略してエンプラとも呼ばれます。 ・PC(ポリカーボネイト)、ABS樹脂(アクリロニトリル、ブタジエン、スチレン共重合合成樹脂)などが代表的な種類です。 (2)エンジニアリングプラスチックの置換事例 ・FA自動化部品では、ボールねじのベアリングの循環部で方向転換させるリテーナー部などにエンジニアリングプラスチックが採用されています。タグ:
- 石油などの地下資源の枯渇問題や地球温暖化問題などを背景に、自動車ではガソリン車からハイブリッドカーや電気自動車などへの切り替えが急速に進んでいます。エネルギー源としても、CO2削減の狙いで、太陽光発電や風力発電などの実用化競争が各国で繰り広げられています。 この様な技術革新競争のなかで、重要な技術に軽量化技術が挙げられます。軽量化技術について解説します。 (1)軽量化技術の狙い ・運動するものの重量を軽量化すると、エネルギー消費量を軽減できることが軽量化技術の狙いです。 例: (1)自動車の車体材料を鉄系からアルミ合金系に置換して軽量化(【図1】) (2)新幹線の車両材料をアルミ合金化して軽量化 (3)航空機の機体本体のCFRP複合材料比率を増大させて軽量化タグ:
- 機械システムには機構設計図があるように、空気圧駆動システムや油圧駆動システムにも設計図があります。ここでは空気圧駆動システムの設計図について解説します。タグ:
- 組立図から詳細設計の部分組立図に進んでゆく段階で、組立し易い部品形状の設計を心がける必要があります。ここでは、組立し易い部品形状の設計のポイントを解説します。タグ:
- 自動機の設計能力の向上には、多くの設計経験を持つこと、色々な自動機を見て知識量を増やすことなどが挙げられます。しかし、自動機設計の中でも特に位置決めや加工の高精度化に求められる剛性設計などは、高度設計を経験しなければなかなか体得できない暗黙値があります。ここでは、剛性を図面化するポイントを解説します。 ・自動機をはじめ、全ての機械装置には力の作用点があります。 ・ほとんどの機械装置は、この力の作用点で加工や組立などの付加価値を上げる処理が成されます。 ・また、高速駆動する機械装置の場合は、加速度が変化する位置で慣性力が作用します。 ・このような加工力や慣性力は、その反対方向の力となる反力とつりあいを取って機械装置自体が安定して静止できていることとなります。 ・機械装置は、この反力に負けない構造体強度を持っていなければなりません。反力に負けない構造体強度とは、機械装置の試用期間を十分に保証できる必要があります。タグ:
- 自動機は多くの部品の組立による機構ユニットと駆動ユニット、センシング・制御ユニット等で構成されます。この様な複雑な構成を持つ自動機の信頼度の高い設計について解説します。 ・「信頼度」とは、JIS用語として定義された技術用語で、系、機器、部品などが、与えられた条件で、規定の期間中、要求された機能を果たす確率と定義されています。 ・「信頼度」は自動機を構成する全ての組立部品の信頼度の掛け算(直列モデル)で表現されます。 ・信頼度は部品数の掛け算で低下するため、個々の部品の信頼度を上げることよりも部品数を減らすほうが効果は上がります。タグ:
- 組立図の設計を進める過程で、構造がだんだんと明らかになるに従い頭で考えていた構想と違って、懸案が生じてきます。このような場合の対処法をいくつか紹介します。タグ:
- 組立図の寸法記入について解説します。 【図1】はビンゴゲーム機の全体組立図の中の正面図と平面図です。この図の中に寸法記入箇所が5箇所あります。 全体組立図の寸法記入の目的は、装置の代表寸法を示して、装置の概略寸法を理解し、搬入時のチェックやレイアウト情報などに利用します。 したがって、開閉ドア(例:【図1】の赤丸部)などがある場合は、開口状態での全幅寸法なども記入し、レイアウト時のメンテナンススペースの確保などに利用できる図面が好ましい。タグ:
- 非常に多くの機構部品や駆動ユニットで構成される大規模自動機の設計の場合、我流の設計の進め方では色々な問題が後から出てきます。CAD設計に変化したことで、昔の手書き時代の製図の苦労は無くなりましたが、それでも安易に全体設計に着手するとまとまらなくなります。大規模自動機の設計の進め方の要点を解説します。 大規模自動機の全体設計とサブユニット設計 ・規模の大小に係らず自動機は次のような機能分割が可能です。 ・大規模自動機の全体設計は、(1)設置レイアウト情報、(2)全サブユニットの駆動的繋がりを維持させるための配置設計、(3)制御系の仕様統一の指示程度とし、不要な複雑設計に入らないことがポイント。タグ:
- 自動機の部品は形状と寸法で決まりますが、この設計者が決める2つの項目(形状と寸法)は、部品費と自動機の組立費の両者に大きな影響をおよぼします。前号では部品加工費への影響を解説しました。ここでは組立費への影響について解説します。 ・自動機の価格は次のような構成で決まってきます。 ・自動機の部品は次の3つの設計要素(形状、寸法、材料)からなっています。タグ:
- 全ての機械装置はさまざまな部品を組みつけて製作されています。したがって、自動機をはじめ全ての機械装置は部品図が最終の出力情報となります。ここでは自動機の部品図作成のポイントを解説します。 自動機の価格は次のような構成で決まってきます。 自動機の価格=設計費+部品加工費+購入品費+組立費+利益タグ:
- 自動機の部品は、組立図で表現される各図面(正面図、平面図、側面図、断面図など)に部品番号を付けて、部品の組立位置とその状態を図示します。ここでは、部品図の展開について解説します。タグ: