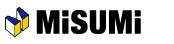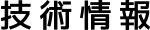金属体の表面を、腐食環境から遮断する方法として、古くから塗装が行われてきました。塗装とは、ペンキを塗ることですが、塗料を金属表面に塗ることによって、塗膜を形成し、これが腐食環境から金属を保護する役目を果たします。
橋梁、建築物、鉄塔、化学プラントなどの陸上構造物、護岸、沖合構造物などの海洋構造物、各種車両、家電製品などの殆どに塗装が施されています。防食対策費の60%は塗装であるといわれています。
塗料は、塗膜を形成する「ビヒクル」といわれる成分に、不溶性の顔料粒子を懸濁させたもので、通常は、これに溶剤を加えて流動性の液体にして、金属に塗布し、これを自然または加熱によって、溶剤を揮発させると、化学反応によって塗膜が形成されます。
ビヒクルとしては、古くは亜麻仁油や桐油など天然産の油が用いられていました。これらは乾性油であって、空気に晒されると酸化・重合して固化し、塗膜を形成します。
顔料としてビヒクルに加えられるものには、着色のためとして、白色には酸化チタン、黒色にはカーボンブラック、青色には紺青などが使われます。塗膜の光沢、塗膜強度、増量などの目的で、硫酸バリウム、炭酸カルシウム、粘土、珪藻土、などが使われています。
耐食性にとって重要なものは防錆顔料であります。昔から、鉛丹Pb3O4、クロム酸亜鉛ZnCrO4などが、下塗り塗料に使われています。これらは、塗膜を透過した水に溶けて金属体の防錆剤として働くからです。
防錆顔料として大事なことは、水に対する溶解度が、低く過ぎず、高すぎないことです。溶解度が低いと、防錆効果が働かないし、高すぎると、短期間に流出してしまうからです。
油性さび止め塗料は身近に使われてきました。これは亜麻仁油など天然産ビヒクルに、鉛丹などの防錆顔料を加えたもので、安価で、手軽に塗れるため広く使われていましたが、高分子重合技術の進歩によって、合成樹脂系の塗膜性能の優れた塗料が使われるようになりました。現在の主流は、フタル酸、塩化ゴム、ウレタン、エポキシ、塩化ビニルなどの樹脂です。
塗装は、方法が簡単であり、どのような形状のものにも適用できるので、多くの場合、他の防食方法に比較して安価でありますが、塗装技術次第では防食性能が大いに異なります。施工面でも検査面でも、一定品質を保つことが難しいという側面もあります。
その理由は、塗膜の形成過程が現場によって異なることや、塗装前の金属体の表面状態が、錆び発生を促進するような状態にあることや、塗膜の密着性を阻害するような状態にあることにも起因しています。つまり、塗装前の素地調整が十分に行われたかどうかによって、施工後の塗膜性能に大きな差を生じます。